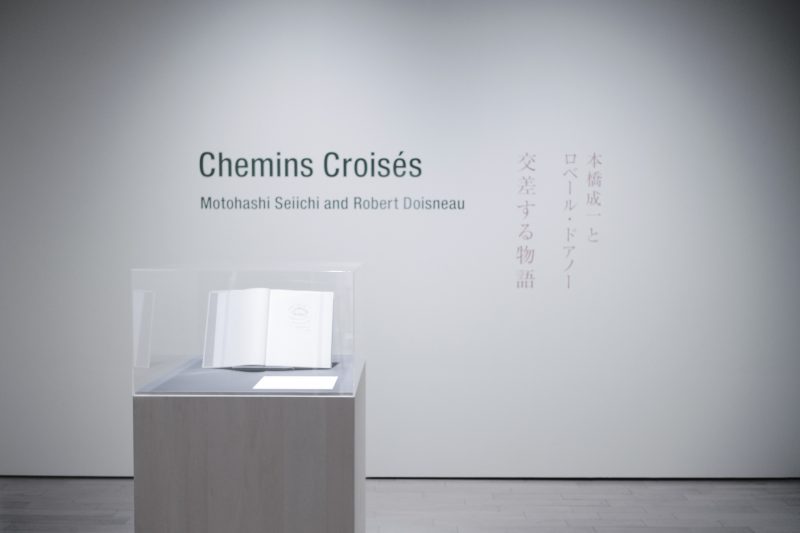建築という事象

広島県福山市にある福山駅は広島市が第二の故郷である私にとって広島の東の玄関口である。ここで途中下車をして、鞆の浦や尾道、竹原という町に出かけることは日常にいながらにして非日常をもたらしてくれる体験である。福山駅の目の前には、このエリアでの移動の拠点となるビジネスホテルが数多く建ち並び、ホームからは白亜の福山城も見える。福山は山陰、山陽、四国の産業や文化の拠点のひとつとして発展してきた歴史を持ち、瀬戸内海に面した地の理を活かし重工業主体の製鉄、造船業など海運業の拠点ともなった。

広島県の福山市と尾道という、風光明媚なのどかなエリアで「ひろしま国際建築祭 2025」が始まった(一部展示を除き2025年11月31日まで開催中)。
私は、秋が始まったようで残暑が厳しく残るわずか一日だけ(しかも、月曜日で美術館での展示は休館)だったが、この日本の西の小さなエリアで開催されている建築祭を訪れることができた。
この「ひろしま国際建築祭」は、2024年1月に設立された福山市に拠点を置く一般財団法人 神原・ツネイシ文化財団(広島県福⼭市 代表者:代表理事 神原勝成)が開催する国際建築祭。今回が第一回目となる。私が訪れた前々日には多くの建築家や関係者が招かれ式典やセミナーが行われたと聞いた。世界が誇る近代・現代建築遺産が今も多く残る瀬戸内海を挟んだエリアにある広島だからこそ、その理由とリアリティを持って開催できる建築祭である

神勝寺 禅と庭のミュージアム
第一回目となる今回の建築祭の開催エリアは福山市とお隣の尾道市。どちらも比較的駅周辺で開催されているから、どの展示会場も初めてこの地を訪れる人にもアクセスがしやすい。
二つのエリアにある美術館、福山駅から少し離れてはいるがバスやタクシーで行くことができる神勝寺で行われている複数の展示は、ぜひ足を伸ばして訪れてみたい。
中でも神勝寺 禅と庭のミュージアム(広島県福⼭市沼隈町⼤字上⼭南91)で行われている、『建築文化再興プロジェクト「成城の家」の写し 一丹下健三自邸の再現・予告展』は必ずみておきたい。
これは、神原・ツネイシ文化財団により、福山の丘の上に現在進行形で計画中の建築プロジェクト「成城の家」(1953年竣工、現存せず)を再び建てる計画の途中報告ともなっている。「成城の家」が竣工した1953年といえば、広島平和記念公園計画のコンペを勝ち取り竣工させた2年前、丹下40歳の年。若き建築家として脂が乗り切ったころである。2018年、東京六本木の森美術館で開催された『建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの』で展示された1/3の模型は迫力があると同時に、この建築の稀有な空間体験をもたらしてくれる。丹念に収集された丹下関連の資料や、丹下の御息女が語る動画からはこの再現プロジェクトの背景が見えてくる。この「家」には丹下と関わりの深かった建築家だけではなく、デザイナー、政治家も集った。また、当時の成城の他の家と同じように、家には塀がなく、築山だけが隣家の敷地との境を示していた。近所の子供たちがこの建築家の家の庭や当時日本の建築には珍しかったピロティの下を駆けずり回って遊んでいたという。
もともとこのプロジェクトは、この成城の家で自身の結婚披露パーティーを行った(当時の所員は成城の家で結婚パーティーを行うのは半ば慣例であったという。なんと愛された建築だったのだろうか)丹下事務所の所員であった建築家、磯崎新が生前熱望していたものでもあったという。

建築文化再興プロジェクト「成城の家」の写し 一丹下健三自邸の再現・予告展

福山駅から黄色い山陽本線に乗り継ぎ、ボックス席で揺られて30分弱。右手斜面にびっしりと家々がつらなり、左手には向島との間に尾道水道が目の前に広がりつつ、尾道の町に列車は滑り込む。尾道駅の少し手前右奥の方に円形の窓を持った古い校舎がみえる。作家、林芙美子(1903-1951)が思春期を過ごし、名作『放浪記』の舞台のひとつにもなった尾道らしい風景が広がる。


アーケードから国道2号線、山陽本線の線路をくぐり、急な石段をのぼり、林芙美子作品にもゆかりの深い千光寺に続く斜面に立つ古民家で、建築設計事務所のOBOGが集う珍しい展示も私が訪れたものの中で印象に残ったものの一つだ。それは尾道の高台にあるスキーマ建築計画(東京)の長坂常が所有するLLOVE HOUSEで開催されている『OPEN LLOVE HOUSE | 尾道「半建築」展』。
建築家としての技や施主や社会とのコミュニケーションがいかに所員やスタッフに受け継がれていくのか。その作家的なスタンスとは裏腹に社会や土地と関わることで成立しうる建築家という職能。スキーマ建築計画を設立して27年が経った長坂常と歴代の所員たちの退所後の繋がりがあってこそ実現しえた、人のものである建築の本来の在り方に立ち返ったような人間臭い展示でありプロジェクトだ。
尾道水道と向島を見下ろす2階大広間には、近々上梓されるスキーマ建築計画の仕様書本のページが止め石に留め置かれている。
建築祭開会と同時に行われた、スキーマ建築計画のOBOGによる3日間にわたり繰り広げられた議論「半トーク」はスキーマ建築計画のYouTubeチャンネルでアーカイブ配信されているから気になる方はチェックしてみては。

OPEN LLOVE HOUSE | 尾道「半建築」展

「スキーマ建築計画のOBOGによる3日間にわたり繰り広げられた議論「半トーク」」
LLOVE HOUSE ONOMICHI / Photo:西川浩史 Hiroshi Nishikawa

LLOVE HOUSE ONOMICHI
尾道エリアの展示としては、建築家ではないが、若手建築家に引くて数多の写真家、高野ユリカの展示『うつすからだと、うつしの建築』(会期:10/4ー 11/3、水曜休)にも足を運んだ。20年前には高齢者の乳母車を売るお店しか開いていなかったような尾道駅前のアーケード商店街だったが、現在は若者が集うショップで賑わっている。このアーケード街の中にある旧銀行、まちなか文化交流館「BANK」の建物で開催されている展示では、近年高野が取り組んでいる、ここ尾道にもゆかりの深い文豪、林芙美子のこの地での足跡を辿るような写真と映像を見せた。緻密なリサーチと作家と土地へのイマジネーション、そしてそれらに対する確かな愛情に溢れ、深く心に残った。

高野ユリカ「うつすからだと、うつしの建築」

高野ユリカ Yurika Kono

高野ユリカ Yurika Kono

高野ユリカ Yurika Kono

高野ユリカ Yurika Kono

スタジオ・ムンバイ / ビジョイ・ジェインが昭和30年代に建てられたアパートをリノベーションし、2018年に開業したホテル施設「LOG」。ここでは、「建築の声を聞く」と題して、大阪のデザインスタジオUMA/design farmによる体験型の展示も行われていて、さまざまな建築のディテールに触れることができる。
尾道のウォーターフロントにあるONOMICHI U2のオリーブ広場、JR福山駅南口、神勝寺無明院の無明の庭には、それぞれ中山英之、石上純也、堀部安嗣の移動型キオスクが設置され、この建築祭を盛り上げる。
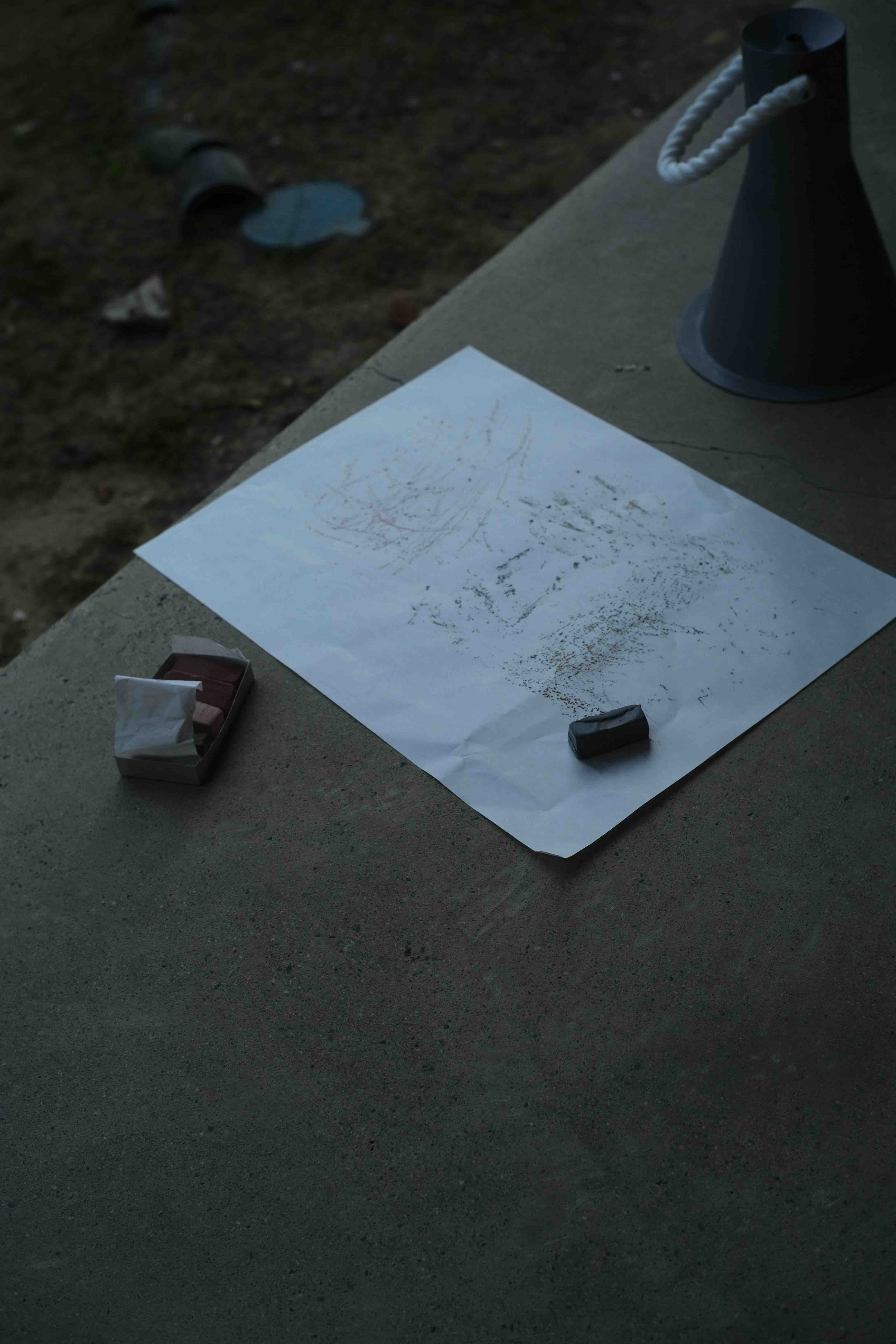
UMA/design farm 「Architecture Voice from LOG「建築の声」を聞く」

中山英之×モルテン「風景が通り抜けるキオスク」

堀部安嗣×ウッドワン「つぼや」

「ZINE」から見る日本建築のNow and Then
第1回となる本展のテーマは「つなぐ「建築」で感じる、私たちの“ 新しい未来”Architecture:A New Stance for Tomorrow」。
本建築祭で感じたのは、そこに関わった「人」と「建築」との蜜月ともいえる、事象としての建築やイベントを評する言葉としては、いささか曖昧な「関係性」という言葉。


Photo:西川浩史 Hiroshi Nishikawa
「再現」、「再生」、「再会」。これほどまでに愛され続ける建築と建築家像とはいかなるものなのだろうか。これは単なる建築家の実作や実績を世界に向けて披露する建築祭、建築展ではなかった。人と、建築を思う人たち、そしてその思いを感じる機会としての関係性を実感する建築祭だった。だから、ここに参加している建築家たちも人や今在る社会に対して偽ることのない、私にはそう思えた。そしてこの建築祭を作りあげ実現した神原・ツネイシ文化財団とその関係者、これまで財団関係者と長年関わってきた数多くの建築家たち。その人々たちの建築や人の暮らしへの愛着を感じた。
ひろしま国際建築祭は今後3年に一度の開催を目指すという。その間にも福山エリアを中心に神原・ツネイシ文化財団による建築プロジェクトが着々と進行する。物や事象としての建築は、つまるところ「人」なのだということを私は瀬戸内の小さなエリアで開催中の、この建築祭で感じることができた。

テキストと写真=加藤孝司 Text & Photo Takashi Kato
- ひろしま国際建築祭2025
- 会場:広島県福山市、尾道市、美術館や神社、及びサテライト会場
- 開館時間:各会場に準ずる(HPにて要確認)
- 休館日:各会場に準ずる(HPにて要確認)
- 料金:一般当日販売 3000円(オンライン販売2,500円) / 高校生以下および障がい者無料)

- #88
- #Adam Ianniello
- #Agnieszka Sosnowska
- #ART
- #Bryan Schutmaat
- #Hiroshima
- #Interview
- #JENN KANG
- #Johanna Tagada Hoffbeck
- #JohannaTagadaHoffbeck
- #Kanadehamamoto
- #Kei Ono
- #Masahisa Fukase
- #Masato Ninomiya
- #Matthew Genitempo
- #Ohenro
- #review
- #Shota KONO
- #ShotaKONO
- #Takashi Kato
- #Thomas Boivin
- #Tokushima
- #TOP
- #アユニ・D
- #アート
- #インタビュー
- #ジョアンナ・タガダ・ホフベック
- #トマ・ボワヴァン
- #フォト
- #三部正博
- #井崎竜太朗
- #今井智己
- #内藤礼
- #写真
- #加藤孝司
- #堀 裕貴
- #小野啓
- #山口息吹
- #山本康平
- #岡崎果歩
- #建築
- #本多康司
- #根本絵梨子
- #池谷陸
- #池野詩織
- #渡邉りお
- #渡邊りお
- #渡部敏哉
- #温陽民族博物館
- #笠原颯太
- #編集長日記
- #諏訪万修
- #野口花梨
- #長田果純