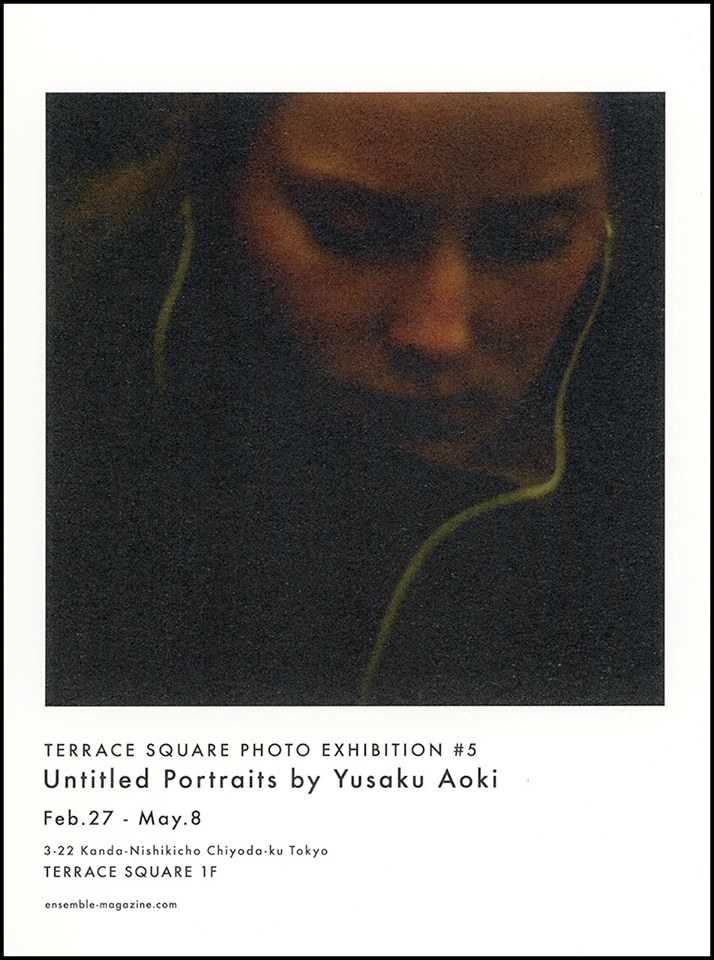建築家として重要な建築を手がけながら、街づくりにも関わり、大学で教鞭をとり後進の育成にも力を注ぐ藤村龍至氏へのインタビュー。
後編では、集合的な知を活用する設計手法や、「縮小」していく都市や地方都市における建築の可能性、変わりゆく風景に対し批判的に乗り越えていく、建築家としての挑戦についてお話を聞いた。
<前編はこちら>
集合的な知を活性化する「間のメタファー」
 TOTOギャラリー・間「ちのかたち― 建築的思考のプロトタイプとその応用」展示風景(2018)
TOTOギャラリー・間「ちのかたち― 建築的思考のプロトタイプとその応用」展示風景(2018)提供:RFA
ー 寛容さと多様性の共存、建築においてそれを可能にするのはどのようなことだとお考えですか?
集団でコミュニケーションはするのだけれど、片方で建築的な抽象性は担保するのが大事だと思っています。 その時重要になりそうなのが時間と空間双方における「間」という概念です。
西洋の哲学では時間と空間という2つの大きな概念がありましたが、日本では明治時代にそれらの概念が入ってくるまで、時間も空間も同じ「間」という概念として理解されていました。磯崎新さんは1980年代にパリで行った「間」展という展覧会ではそのことを大きく問題提起されました。
私自身は現在、デジタルの技術が進化したことで生まれたコンピューターアルゴリズムやディープラーニングといった技術もそのような「間」のメタファとしてみることができないかと考えています。
あるスパン、単位を設計し、それをモジュール的に反復しながら、そのなかで変化させるというクリエイションの仕方があって、集合的な知を設計する方法として「間」の再解釈をすると面白いと思っています。
最近の私たちの設計でも、時間的なリズムと空間的なリズムの交差を意図的に取り入れていて、例えば二週間ごとに5案つくると決めその講評を集団で繰り返したり(「鶴ヶ島プロジェクト」2011-2016)、さいたま市大宮駅東口駅前おもてなし公共施設「OM TERRACE」(2017)では、建築を取り巻く外装材から手すりに至るまで300mmごとの材の反復と変化で設定しています。
人と人のコミュニケーションのセッションと、ものともののセッションの両方に、「間」というメタファーを応用しているのです。
 提供:RFA
提供:RFA
 写真:Takumi Ota
写真:Takumi Ota
「OM TERRACE」のプロセス模型群とマテリアル
ー そうすることでコンピューターを演算しているだけでは見えてこない、人の営みやふるまいが自然なかたちで設計に取り込まれていくということでしょうか。
そうですね。それらが設計をする際の基本的な単位になっていきます。
ー それは人間が介在しないと生まれてこないコンピューター的なプロセスということでしょうか。
機械言語をただそのまま扱っているだけでは「建築物」になっていきません。
人間の認知やニーズをいかに理解し、それをどう機械言語に置き換えていくか、機械言語で生成されたジオメトリをそうやってリアルな建築物に戻していくか、という関係のとり方は、まだまだ成功例が少ないのが現実です。
人間の認知には限界があり、機械による観測がより豊かな知識をもたらしますし、単にシミュレーションの結果をかたちにしたようなものは、人間に対してあまり効果的に働いていないように思います。人と機械を取り結ぶような関係性のデザインが必要だと思っています。
今回のギャラリー・間の展示「ちのかたち」では「Deep Learning Chair」という椅子を展示しています。
それはどういうものかというと、インターネットの画像検索で検索エンジンにそれぞれ異なる言語(中国語・英語・スペイン語・日本語等)で「椅子」という言葉を入力するとまったく違うものが画像として表示されます。
それをもとにデータセットを生成し、コンピューターに深層学習してもらうと、人類が考える椅子のかたちを切り出すことができます。それは建築のかたちにも応用可能だと思います。
 「Deep Learning Chair」(2018)
「Deep Learning Chair」(2018)提供:RFA
 構造最適化設計によって生み出された曲面屋根をもつ「すばる保育園」(2018)
構造最適化設計によって生み出された曲面屋根をもつ「すばる保育園」(2018)写真:Takumi Ota
ー そこには藤村さんがゼロ年代から掲げていた「批判的工学主義」の考え方が貫かれているわけですね。藤村さんは当時、都市の景観を陳腐なものにしているマンションや高層ビルが無批判に自動的につくられているという現状に対し、それに対する乗り越えを標榜されていました。
高度な計算やシミュレーションは我々に豊かな知見をもたらしてくれますが、放っておくと新しいパターンを生み出してしまいます。
そこに意志をもった人間が時々介入することで形骸化を防いだり、批判的な見方を提示したりして、物事を柔らかくしていくことが必要なのではないかと考えています。
それはおっしゃるようにゼロ年代に提示した「批判的工学主義」の考え方の延長にあるものです。
その考え方は都市だけでなく、「Deep Learning Chair」のような家具の設計や、「すばる保育園」(2018)のやわらかな形態が示すように、自然の風景との関係を設計することにも応用可能だと考えています。
※「批判的工学主義」とは。
ゼロ年代後半の2007年に、藤村さんと同世代の社会学者である南後由和さんらと共に提唱したコンセプト。
技術依存や専門分化が進んだ1990年代以降の現代社会では量とスピードが求められ、建築家が不要と言われるようになった。
そのままでは建築家の仕事は、インフラの上で見せかけの表層と戯れるしかなくなってしまうのではないかという問題意識から、そのような状況を、単純に否定するのでも肯定するわけでもなく、批判的に乗り越えるための考え方。
20世紀型都市の未来像
ー 藤村さんはゼロ年代以降、青年期を過ごした東京郊外にある東洋大学で教鞭をとり、埼玉周辺でのプロジェクトを勢力的に展開されていました。一昨年よりあらたに都心の東京藝術大学で教鞭をとられています。最近は都市への視点はいかがですか?
ゼロ年代以降も都市への眼差しは持ち続けていました。ひとつには新しい風景としての都市への介入。
一見大海原にみえる質より量が求められる均質な場所に、違いを生み出そうという「BUILDING K」から続く問題意識です。埼玉で活動するようになってからはそこに人々の集合としての都市への介入、という政治や経済の視点が加わりました。
今はさらに歴史的な視点を導入しようとしています。20世紀を通じて構成された近代的な「大都市」という概念を、あらためてここで総括する必要があるということです。
ー そこにはどのような問題意識や課題があるのでしょうか。
超高齢化や人口減少というような、人口に関わる課題が大きくなっています。構図そのものは1960年代に似てきていて、そこにはさまざまな共通点があります。
大きなスケールでいえばそれは、列島のなかに東京というメガシティがあって、そこに地方からたくさんの人が集まるというものです。
例えば群馬の人が前橋や高崎では止まらずに東京に流れていってしまう。その流れに対し、かつて田中角栄はその流れを逆流させるのだ、といって全国に工業都市をばら撒いて人口を逆流させて、ふるさとを取り戻す「日本列島改造論」を提案しました。
その試みは瞬間的には効果を生みましたが、結局東京に人が集まる動きは止まらずメガシティ化し、そしてグローバル化して行きました。一方、地方都市はますます縮小していきました。最近では徳島県神山町のようにそれを逆手にとった動きもでてきているのですが、大都市自体はますます高密度化しているのが現状です。
でもやがて超高齢化や直下型地震によって大都市にも限界が来るでしょうし、大都市の周辺では既に課題が顕在化しています。
ゼロ年代に入って日本で起こっている取り組みは、地方は「地方創生」、大都市は「都市再生」という、ある種の大改修でもう一度日本列島全体に手を入れていこうというものですが、大都市郊外についてはあまり取り組みがありません。
郊外の問題は高齢化のスピードを考えると、今もっとも急いで解かなければならない課題だと思っています。
 写真:Takashi Kato
写真:Takashi Kato
 写真:Takashi Kato
写真:Takashi Kato
今、そうした日本の大都市の歴史的な成果や現在の課題について、建築の視点でまとめようとしています。
1968年に霞が関ビルが建ってから、この50年で単独で建っていた超高層ビルも、「ステーションシティ」といわれるようなインフラと建築が一体化した複雑なものに進化しました。
初期の新宿副都心のように大きな空地に超高層をひとつひとつ建てるだけではなく、赤坂のアークヒルズ以降はもともとある既成の市街地を改造して再開発するという流れになり、現在では既成のインフラまで更新して超高層を一体で再開発するという流れがでてきました。
その日本型巨大開発の歴史のひとつの到達点で最新型が渋谷駅周辺開発です。渋谷駅という、既存の鉄道にデパート、地下道や地下を流れる河川などが複雑に絡んでしまっているのをひとつひとつほぐしていって、それを耐震改修して上に超高層を6本つくる計画が進行中です。
基盤と一体化した建築のあり方は、昔のお城にみられる石垣と天守閣からの日本の伝統芸のようなものです。
それは一説には土木と建築に置き換えられていくといわれるのですが、それが現代では土木=インフラ改修、建築=まちづくりと呼ばれるようになり、その集大成が渋谷や品川であり、それがいまでは郊外にも波及し、私がいま携わらせていただいているさいたま市大宮にも及んでいます。
 道路利活用社会実験「おおみやストリートテラス」(2017)
道路利活用社会実験「おおみやストリートテラス」(2017)提供:UDCO
ー 大宮のお仕事ではでは建築家としての藤村さんはどのような役割を担っているのでしょうか?
行政と地元の人の間に入りコーディネーター役をやっています。大宮では2016年からの10年を「運命の10年」と呼んで大きな公共投資が仕掛けられつつあるのですが、今後の人口減少を考えた時に、今が大きな改修を仕掛ける最後のチャンスなのだと思います。
世界的にみれば渋谷のような複雑な開発を行っている都市は日本だけなので、これは都市開発や建築的な視点からみれば日本型のプロダクトだと位置づけることも可能です。
そうした日本独特の建築的な成果物は、日本国内での建設が一段落する東京オリンピック・パラリンピック以後は、急成長を続けるベトナムやインドネシアなどの東南アジアの諸都市に応用されるようになり、今後、日本の建築家関係者は東南アジアとのあいだを激しく往復するようになると思います。
それを1923年の関東大震災後の満州へのインフラ進出の歴史の反復と見ることもできるでしょう。
 3.11以後の日本の進む道を描く「希望の軸」
3.11以後の日本の進む道を描く「希望の軸」写真:Kenshu Sintsubo
 写真:Takashi Kato
写真:Takashi Kato
都市の隙間にある魅力的な空間
ー そのような大きな視点での都市の新陳代謝にもワクワクするのですが、都市の隙間のような小さくても魅力のあるものは今度どうなっていくとお考えですか。
メガシティ東京のなかの、渋谷や池袋、銀座などの大きな街だけではなく、蔵前や谷根千、神田といった、アメリカでいえばポートランドなどもそうかもしれないのですが、都市的な利便性を持ちながら、伝統や、ローカルならではの親密さが街に人々を引き寄せている現状があり、そこにこそ本当の暮らしがあるように思っています。
東京の下町エリア、蔵前や浅草、清澄白河や、ポートランドもそうですが、ある時期開発から乗り遅れたからこそ、逆説的にいま先端になりえたとも言えると思います。
東京以外でいえば福岡が近いのかもしれませんが、工業化に乗り遅れたから結果的に最先端という、そういう街はどの時代も面白いと思っています。文化的にはむしろそうしたエリアが東京の新しいイメージをリードしていくと思います。
東京の小さな町でいえば、ここ数十年変わらず人気のある谷根千は、80年代に作家で市民運動家の森まゆみさんたちがエリア全体をブランディングしたことが実を結んだような気がします。
最近では宮崎晃吉さんのHAGISOが新しい世代の動きを作っていますね。そのような一見小さなものでも、些細なきっかけでエリアが栄えたり衰退していったりということを繰り返していくんだと思います。
最近上野に越してきて、この街に対する見方が全然変わりました。
引っ越す前は上野駅周辺のアメ横などの猥雑としたイメージ強くて人が生活する街のイメージがなかったのですが、暮らしてみると上野公園などの広大な緑地があり、走ると気持ちがよく、生活の場所としてもいろいろなものが揃っている街で暮らしやすい場所です。
 写真:Takashi Kato
写真:Takashi Kato
ー 藤村さんは神田神保町あたりには来ることはありますか?
はい、ときどき行きます。
ー 神田界隈は街としての歴史があり、長い時間をかけて培われてきた文化や人と街とのつながりがいまもあり、銅板建築や老舗のお店がまだ健在です。
現在街にはオフィスビルも増えているのですが、働いている人たちが地域の祭りや催事に参加したり、下町らしい祭りの賑わいが生み出す街のスケールがまだ生きている街だと思います。
ポイントはまだ住んでいる人が残っていることだと思います。そこですごす時間が長くなると、人は街に対して責任をもつようになります。なるべく若い世代の人たちで住みたいと思わせるような取り組み、特に仕事の場としての魅力づくりをすることで、街がより活性化していくと思います。
ー 上野に暮らし、事務所も上野に移されました。そして上野にある東京藝術大学で建築家の准教授教鞭をとり、藤村さんご自身の地域との関わりはいかがですか?
東京大学の中島直人さんにお声がけ頂いて「東京文化資源会議・上野スクエア構想検討委員会」という、上野のまちづくりの話し合いに参加させて頂いています。
そこで地元の方々と意見交換するようになりましたが、意外にも上野公園と上野のまちの関係が歴史的に希薄だということを知りました。
近年公園のリニューアルをしてたくさんの人が集まるようになり、盛り上がっているように見えますが、街とインフラがこれほど隣接しているにも関わらず、地元の人はあまり最近の公園の動きをご存知ないし、そもそも公園を利用することも少ない現状があるようです。
ニューヨークのように公共と民間が連携し、公園の一部を地元の人たちが活用して活性化していくということをやるには絶好の場所だと思うのですが、いまのところそれはあまり活発ではありません。
アメリカはそれらの課題を乗り越えて、既存のインフラを使って地元の人たちが商売をしたり、若い人たちが公園でお店を出して、パワーアップして地元に戻っていくということをどんどんやらせています。
日本でも地方都市ではそのような動きがでてきていますが、上野でもできるはずで、そのような動きを作ることで公園の中に快適に過ごすことができる場所が増えてくればよりよいのかなと思っています。
藝大とまちの関係の発展も課題ですね。毎年9月に行われる藝祭ではものすごいクオリティで学生が屋台や神輿をつくり、一般来場者も多く集まりエネルギーも感じるのですが、ややキャンパスの中に閉じている印象もあります。例えば鶯谷など周辺の空洞化しつつある既存のまちともっと関係が結べると面白いかも知れません。
 「東京藝術大学の神輿」
「東京藝術大学の神輿」写真:藤村龍至
ー 最後に建築家という存在について質問をさせてください。10年前に私が行わせていただいたインタビューの際、藤村さんは、90年代以降の現代社会では建築には量とスピードが求められ、建築家は不要と言われているとおっしゃっていました。あれから10年経ち、その状況は変わったと思われますか?
2005年に日本の人口がピークを迎えて、東日本大震災が決定機となって社会のモードが大きく変わりました。
「縮小」を自覚するようになり、将来に対する不安が漠然と生じてきて、将来を先読みする存在が求められ、1960年代に未来を積極的にデザインしようとした丹下健三や黒川紀章のような人が登場した頃の社会状況に戻ってきている気がします。
そのような預言者のような存在にもし建築家が再びなれたとしたら、社会的にはまた違う役割がでてくるのかなと思っています。
ー そのような存在に藤村さんがなると。
理論はできたのであとは作品でそれを示していくつもりです。10年前のインタビューでも年代別のアクションについてお話しましたが、私が30代のときに掲げた目標は40歳で10人、50歳で100人、60歳で1000人のスタッフを抱えると言っていました。40歳で10人はなんとか達成することができました(笑)。次は50歳で100人のチームを持てるように頑張るということではないでしょうか。
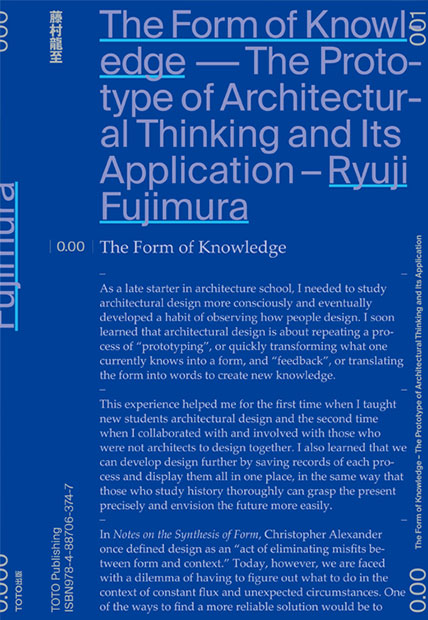 『ちのかたちー建築的思考のプロトタイプとその応用』(2018)
『ちのかたちー建築的思考のプロトタイプとその応用』(2018)提供:RFA
写真と文=加藤孝司

- #88
- #Adam Ianniello
- #Agnieszka Sosnowska
- #ART
- #Bryan Schutmaat
- #Hiroshima
- #Interview
- #JENN KANG
- #Johanna Tagada Hoffbeck
- #JohannaTagadaHoffbeck
- #Kanadehamamoto
- #Kei Ono
- #Masahisa Fukase
- #Masato Ninomiya
- #Matthew Genitempo
- #Ohenro
- #Rei Kuroda
- #review
- #Shota KONO
- #ShotaKONO
- #Takashi Kato
- #Thomas Boivin
- #Tokushima
- #TOP
- #アユニ・D
- #アート
- #インタビュー
- #ジョアンナ・タガダ・ホフベック
- #トマ・ボワヴァン
- #フォト
- #三部正博
- #井崎竜太朗
- #今井智己
- #内藤礼
- #写真
- #加藤孝司
- #堀 裕貴
- #小野啓
- #山口息吹
- #山本康平
- #岡崎果歩
- #建築
- #本多康司
- #根本絵梨子
- #池谷陸
- #池野詩織
- #渡邉りお
- #渡邊りお
- #渡部敏哉
- #温陽民族博物館
- #笠原颯太
- #編集長日記
- #諏訪万修
- #野口花梨
- #長田果純